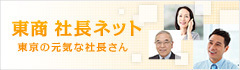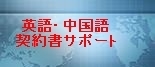大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
|---|
アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
|---|
配偶者居住権の注意点
相続する自宅を居住権と所有権に区分し、残された配偶者が
居住権を相続し、子などが所有権を取得する制度です。
相続する金融資産が少ない場合、自宅を配偶者が相続することで、
配偶者が金融資産を十分に取得できず、
将来の生活資金が不足する場合があります。
あるいは、住宅を売却して遺産を分割しなければならないような場合は、
配偶者の住む家がなくなってしまう恐れがあります。
このように、残された配偶者の居住場所と生活資金の確保が
この制度の目的です。
配偶者居住権は、住んでいた配偶者が亡くなると、
消滅して、所有権を相続した子などが取得することになります。
この配偶者居住権を設定する場合は、必ず登記が必要となりますので、
登記簿で配偶者居住権が設定されていることを確認できます。
また、配偶者が居住を止めて家を売却するような場合は、
配偶者居住権の放棄となり、配偶者居住権の評価額に対して、
子等の所有権者に贈与税が課税されますので注意が必要です。
配偶者居住権の評価額も消滅し、相続税の課税対象ではなくなります。
配偶者居住権の評価額は、建物の耐用年数や配偶者の年齢等により
計算されます。
設定される場合は、相続に詳しい税理士等の専門家に
ご相談されては如何でしょうか。
配偶者居住権の仮登記
相続発生後に、配偶者の居住場所を確保するための
配偶者居住権の設定は、生前の死因贈与契約でも成立します。
私文書で作成する場合は、紛争にならないよう贈与者と受贈者が署名し、
両名の印鑑登録証明書を添付したうえで、
実印を押印することが望ましいと思います。
ただし、より居住権の設定を確実にするためには、公正証書による作成を
お勧めいたします。
印鑑登録証明書や戸籍謄本等が必要なことや、
公証役場に出向かなければならないことは非常に負担であり、
加えて公証費用も掛かりますが、より確実な方法だと思います。
また、作成された公正証書により、配偶者居住権設定を仮登記
することもできますので、親族や不動産業者等の第三者も
配偶者居住権の設定を確認できます。
遺言書にて配偶者居住権を設定する方法もありますが、
親族により配偶者の居住権が脅かされるような危惧があれば、
生前にこの仮登記をしておけばより安心です。
仮登記時は不動産価額の1000分の1の登録免許税を
支払う必要がありますが、
本登記時に相殺されますので無駄にはなりません。
詳しくは相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
お問合せ・ご相談はこちら
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
| 対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
|---|
無料相談実施中
サイドメニュー
お役立ち情報
相続手続サポート
その他のサービス
事務所紹介
お客様相談室
フォンタナ
国際行政書士法務事務所
住所
〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12
アクセス
電車では「雑色駅」より徒歩7分
営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
主な対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など