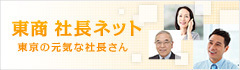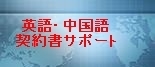大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
|---|
アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
|---|
相続の放棄
亡くなられた方に、財産を上回るような借金や、保証人としての債務等が
有った場合、相続人は相続を全て放棄することができます。
詳しい申請のやり方は下記の通りです。
【誰が申請をできるか】
相続の放棄を申述できるのは相続人です。
ただし、相続人が未成年者であったり、
被成年後見人の場合は、特別代理人の選任を行い、
家庭裁判所の選任審判書が必要となる場合がありますので、
注意が必要です。
【いつまでに申請するか】
相続放棄の申述は、相続が開始したことを知った日から3か月以内です。
ただし、債務の存在を知らなかった場合は、債務の存在を債務の存在を
知った日から3か月以内となります。
【どこに申請するか】
亡くなられた人の最後の住所地の家庭裁判所に申述書を提出します。
東京23区であれば、東京家庭裁判所に提出します。
一部の島を除き、23区外であれば、八王子、伊豆大島、立川の
家庭裁判所の出張所、支部となります。
大田区の場合、大田区役所の近辺に家庭裁判所が有ると勘違い
している方がいらっしゃいますが、
23区の家庭裁判所は、霞ヶ関となります。
【費用はいくらか】
① 収入印紙 ¥800(相続人一人当たり)
② 連絡用の郵便切手 ¥400程度
【どのような書類が必要か】
① 相続放棄の申述書
② 被相続人の住民票の除票
③ 被相続人の戸籍謄本(3か月以内のもの)
(注) 配偶者以外の者が放棄する場合は、
下記の書類も必用となる場合があります。
●放棄する人の戸籍謄本
●被相続人の出生から死亡時までの、連続した戸籍謄本
●放棄する人の戸籍謄本
●被相続人の父母の除籍謄本
(年齢によっては、祖父母の謄本も必用)
④ 第三順位や代襲相続人の場合は、
相続関係説明図が有った方がよい場合もあります。
⑤ 先順位の相続人が相続の放棄をした結果、
兄弟姉妹等が相続人となる場合、先順位の者が放棄したのかを確認する
こともできます。
このような場合は、家庭裁判所に対し、「相続放棄・限定承認の申述の有無
についての照会申請書」を提出することで確認できます。
被相続人が遠縁で、付き合いも途絶えていたような場合、
相続人を確定するのにかなりの時間を要します。
債務が有ったことが判明した場合、
速やかに弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
相続放棄は時間との勝負ですので、速やかに行動に移すことが大切です。
お問合せ・ご相談はこちら
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
| 対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
|---|
無料相談実施中
サイドメニュー
お役立ち情報
相続手続サポート
その他のサービス
事務所紹介
お客様相談室
フォンタナ
国際行政書士法務事務所
住所
〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12
アクセス
電車では「雑色駅」より徒歩7分
営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
主な対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など