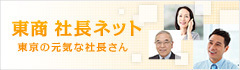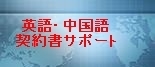大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
|---|
アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
|---|
従来の小規模宅地等の特例では、居住用の宅地に関しては
240㎡までが80%評価減とされていました。
しかし、平成26年の改正により、この240㎡が330㎡に拡大されました。
それに加え、400㎡までの事業用宅地に関して、従来は居住用宅地の
評価減と合算され、別途、適用することはできませんでした。
つまり、自宅の敷地を240㎡評価減した場合、
事業用などの他の土地に関して評価減はできませんでした。
しかし、このたびの改正案では、
居住用330㎡+事業用400㎡、合計730㎡まで
80%の評価減ができるようになります。
つまり、自宅が330㎡、商店、工場等が400㎡で、合計730㎡の土地を
所有している方は、その合計が80%減額され、
言い換えれば146㎡程度の評価額で済むことになります。
(330+400)X0.2
ある大田区の土地の路線価を30万円/㎡とすると、
730㎡で評価額は2億1,900万円ですが、
この特例をフル活用できれば、評価額は4,380万円となり、
その評価減額は1億7,520円にも達します。
このため、事業継承を予定されている方、
及び広めの居住用の土地をお持ちの方には朗報です。
この小規模宅地等の特例改正を上手く活用すれば、
相続税を軽減できる方もいらっしゃいます。
ただし、相続税の基礎控除が大幅に減額されますので、
手放しでは安心できません。
以前に税理士等に相続税の試算を依頼された方もいらっしゃると思いますが、
この改正に準じて再試算を依頼されることをお勧めいたします。
尚、勘違いされている方が多いのですが、遺産分割協議が申告期限までに
できない場合、この特定は適用されませんので、
このような場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を
申告書と一緒に提出して分割協議成立後、4か月以内に提出することにより、
更生の請求ができます。
つまり、一旦は法定相続分に順じた申告を行い、
協議が成立した後に、申告をやり直すということです。
単に見込書を提出するだけでは受理されませんので、注意してください。

また、2所帯住宅を親子で所有されて御一緒にお住いの場合、
区分所有で登記されていると、この特例は適用されません。
特例を適用されたい場合は、共有登記への変更が必要です。
ただし、専門家に登記変更を依頼すれば、手数料や登録免許税
も発生しますので、費用対効果を計算して、
どちらが得かを検証されることをお勧めいたします。
及び、相続前の3年間に本人、あるいはその配偶者が所有する
家屋に住んだことのないいわゆる「家なき子」に関しても、
この特例が適用されますが、
留意すべきは、「6親等以内の親族」や「3親等以内の姻族」でも
この「家なき子」になれることです。
例えば、子は自分が購入したマンションに暮らしていれば
親が所有する家の相続では「家なき子」にはなれませんが、
遺言で家を相続させるとしたアパート暮らしの孫であれば
「家なき子」になれる場合があります。
以上、適用条件が多々ありますので、
相続に詳しい税理士にお問合せください。
小規模宅地の特例の適用厳格化
いわゆる「家なき子」の適用条件が2018年4月以降に発生する
相続より厳格化されました。
相続開始前の3年間に、3親等以内の親族や、関係する法人名義の家に
住んでいた人は、小規模宅地の特例を使えなくなります。
住んでいる家を親族名義に変更したり、社団法人を設立して
土地・家屋を法人名義にすることで、
特例の適用を受けて大幅な節税を図る人が多かったようです。
また、孫に相続させる場合にも、孫が相続前の3年間に
3親等以内の親族の持ち家に住んでいると、この特例は使用できません。
被相続人の自宅に小規模宅地の特例が適用されるためには、
相続人の家の確保という、この特例の本来の趣旨に基づき、
同居の相続人や賃貸住宅等に居住する相続人となる必要があるようです。
ただし、相続人だけが被相続人と同居し、家族は持ち家に残すような場合、
同居の実態が調査されることがあります。
住民票を移すだけの形式的な同居は認められません。
また、貸付事業用地の特例を使うために相続の直前に土地を購入して、
駐車場等として貸付ける場合も、相続まで3年超にわたって貸付事業を
していなければ認められません。
小規模宅地等の特例の適用件数は、相続税申告件数の約半数とのことですので、
今後の申告には注意が必要です。
また、相続人の一人が自分が被相続人の自宅を相続するものだと決めつけ、
独断で相続税対策を実行したものの、
相続発生後に他の相続人の同意が得られず、
結果的に相続税対策が無効となり、場合によっては損害をも被るような
事例もあり得ますので注意が必要です。
相続税対策を練る場合は、事前に専門家のアドバイスを受けて
公正証書遺言を作成したり、
税理士を交えて他の相続人とも協議されることをお勧めいたします。

お問合せ・ご相談はこちら
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
| 対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
|---|
無料相談実施中
サイドメニュー
お役立ち情報
相続手続サポート
その他のサービス
事務所紹介
お客様相談室
フォンタナ
国際行政書士法務事務所
住所
〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12
アクセス
電車では「雑色駅」より徒歩7分
営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
主な対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など