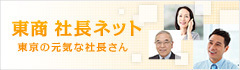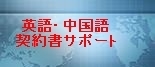大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
|---|
アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
|---|
10年以上前の相続
令和5年4月1日より、相続開始から10年以上経過した場合、
原則として、法定相続分により遺産分割されることとなります。
ただし、令和10年3月31日までの期間であれば、従来の遺産分割協議ができます。
また、相続人全員が同意すれば、10年経過後でも分割協議が可能とされています。
この改正で最も影響を受けるのは、被相続人からの生前贈与(特別受益)と
被相続人の介護、看護等の寄与分がある場合かと思います。
相続開始から10年経過すると、これらの権利・義務が影響を受けます。
何れにしましても、長期間にわたり遺産分割が完了していない場合は、
相続人間で協議、あるいは家庭裁判所に調停の申立て等を
速やかに行う必要があります。
お困りの方は、相続に詳しい行政書士、弁護士、司法書士等の専門家に
ご相談されることをお勧めいたします。
相続法の大改正
民法が大改正された中、相続法においても大きな改正が法務大臣の
諮問機関で議論された結果、下記通り決定されました。
① 【配偶者の法定相続分の引上げ】⇒見送られました。
現在の相続法では、配偶者の法定相続分は1/2で固定であり、
婚姻期間が1日であろうと、50年であろうと、相続割合に差は全くありません。
これを、婚姻期間が20年〜30年と、長期な場合には、
1/2から、2/3に引き上げるというものです。
相続時の妻の高齢化により、妻の生活を保護することがその趣旨のようです。
(配偶者の法定相続分は、1980年に1/3から1/2に引き上げられました。)
② 【所有財産が増加した場合の分割】⇒見送られました。
結婚後に所有財産が一定以上増加した場合、その割合に応じて、
配偶者の分割割合を増やすという案です。
③ 【妻に居住権を付与する】⇒制定されました。
夫が遺言等で自宅を第三者に遺贈したり、親族に贈与したような場合、
妻は自宅に住み続けることができなくなるため、
妻に居住権を認めるというものです。
ヨーロッパの一部の国では、夫の死後に妻が自宅から追い出される事例が
多発して、大きな社会問題となったため、既にこの居住権を制定しています。
④ 【寄与分の認定】⇒ 制定されました。
例えば、妻がどんなに義理の親の介護や看護を行っても、
遺言でもない限り、金銭を受領する権利はありません。
そのような人のために、相続人に対して金銭の請求権を付与するというものです。
海外には、このような権利を広く認めている国もあります。
⑤ 【自筆証書遺言の形式緩和】⇒制定されました
現在の法律では、自筆遺言は全て自筆しなければなりません。
よく有効性が問題になる例としては、相続させたい銀行預金の
口座番号が誤っていたとか、不動産の登記地番を、誤って住所で
書いてしまったなどです。
これらの財産目録をパソコンで作成しても有効とするものです。
海外には、録音、録画の遺言を認めている国もあります。
これらの改正は、高齢となった配偶者の保護や、不公平感の是正といった
評価すべき試案であるものの、抽象的な権利付与が相続の争いを
助長しかねないとの意見もあるようです。
法務省では、今後数カ月間に意見公募を実施するとのことです。
【上場株式評価の見直し】⇒見送られました。
上場株式の相続税の評価を90%に引き下げる金融庁の要望は、
死亡直前に株式を購入して租税回避をすることが可能となるとの
財務省の指摘により、2017年度の税制改正では見送られました。
一方で、上場株式の物納の順位を繰り上げて、株価が相続時に比べて
物納時に下落しても、相続時の時価で評価できるようにするようです。
2019年より施行の法規制
2018年7月の参院本会議にて、以下の相続法改正が可決、成立致しました。
これらは原則的に2019年7月1日より施行されましたが、
一部は段階を経て施行されます。
① 「配偶者居住権」の創設ーーー(2020年4月1日施行)
配偶者が亡くなった後、残された一方の配偶者である相続人が死亡するまで、
自宅での居住権を認めることとなりました。
居住権を得るということは、所有権を得ることに比べて、その評価額が低いため、
預貯金、現金等の遺産があれば、結果的にそれらを多く相続できることとなり、
残された配偶者の老後の資金を増やすことができます。
ただし、権利を確保するためには、法務局で登記をする必要があります。
登記しない場合は、第三者に対抗できないので注意が必要です。
及び、この移住権は、相続税の課税対象となる点にも注意してください。
② 相続財産からの住居の除外
婚姻期間が20年以上ある夫婦の一方が、住居を生前贈与、
あるいは遺言で贈与の意思表示を行った場合、
住居を遺産分割の対象から除外できるようになります。
これも残された配偶者の老後資金の増加につながります。
③ 寄与料の請求権の創設
現行法では、法定相続人ではない嫁、婿、甥姪等が介護や看護をしても、
寄与分として遺産をもらうことは非常に困難な状況です。
苦労して介護、看護した人に何の見返りもないのは納得しがたいという
世間の声に対処したようです。
家庭裁判所が示している療養看護型寄与分によると、
介護日当:¥8,000
日数:500日
裁量的割合:70%
を掛け合わせ、¥280万円とのことです。
この金額の大小は、遺産の総額によって判断が分かれる
のではないでしょうか。
④ 自筆遺言書の保管ーーー(2020年7月10日施行)
自筆遺言書の問題点は、死後に遺言書自体が発見されない、
変造・偽造等がありうる、遺言書の法的な要件を満たしていない等です。
この問題を解決するため、自筆遺言を法務局で保管する制度が創設されます。
もちろん、本人の自筆、及び本人の出頭が条件です。
法務局では、遺言の法的な要件を確認し、遺言者の死亡届が提出されれば、
相続人に通知がいくようにするようです。
ただし、法務局は遺言の内容に関しては関与しないようですので、
注意しなければなりません。
また、財産の目録部分に関しては、印刷でも認められるようになりますので
(2019年1月13日施行)、自筆遺言書の作成が楽になりますし、資産内容が変わっても
書換えも容易になります。
⑤ 預金の仮払い
葬儀費用等の支払のために預金を引き出そうとしても、
遺産分割協議書等を作成して、相続人全員の同意がないと
預金を一切引き出せない金融機関が多いのですが、
預金額の3分の1まで、法定相続分を引き出せる仮払制度が創設されました。
ただし、100万円〜150万円の上限額が設けられるようです。
⑥ 付帯決議
「多様に変化する家族のあり方を尊重し、保護を検討する」
という付帯決議が盛り込まれました。
「家族」とはどのような関係を指すのかが問われます。
現行法では、「家族」とは、戸籍上の家族に限定されており、
事実婚の配偶者に相続権はありません。
一部のヨーロッパの国々では、子の親の半数以上が事実婚の状態であり、
法律婚の両親は少数です。
この付帯決議には、具体的な検討がなされていないようですので、
今後の課題となりそうです。
長期間経過した遺産分割の改正
従来は相続人による遺産分割に期限はありませんでしたが、
被相続人が亡くなってから何十年以上も放置したり、
分割をしないまま、その相続人も亡くなり、次の世代に引き継がれたり
するケースも多くありました。
その結果、持主不明の土地の増加、空家の増加、不動産を活用できない等、
社会的な弊害が問題になってきました。
法務省では、このような問題を解消するために、
令和3年に民法改正を行い、遺産分割協議に10年の期限を設けました。
10年以内に遺産分割を行わない場合や合意ができない場合、
法律に従って自動的に権利確定するように改めたのです。
つまり、遺言書が無いような状況では、法定相続分
または指定相続分に従って遺産を分割するということです。
この共有関係を解消は、法定相続分あるいは指定相続分から、
生前贈与等の特別受益や寄与分を計算して実施されてきましたが、
10年を経過した遺産分割では、それらの算定を不要として、
分割を円滑にするために改正されました。
施工前に開始した相続にも遡及されます。
施行日前に相続が開始された分割では相続開始から10年が経過するとき、
または施行日から5年を経過するときの何れかの遅い方が適用されます。
いろいろな事情で遺産分割を放置されている方は、
この法改正により早期に協議を再開されることをお勧めいたします。
特別寄与料の新設
特別寄与料という制度が設けられましたが、
請求できるのは、六親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族に
限られます。友人や知人は請求できません。
対象とされるのは、無償の療養看護その他の労務の提供に限られます。
いわゆる療養看護型と家事従事型(被相続人の事業に従事して
相続財産の維持または増加に寄与)の場合です。
療養介護では介護報酬日当×療養介護日数×裁量割合で
寄与料が算定されます。
また、特別寄与料は遺産分割調停とは切り離して申し立てができます。
設けられていることです。
特別寄与者が相続開始および相続人を知ったときから6か月以内、
および相続開始から1年以内とされています。
先に特別寄与料の請求をしておかないと、
除斥されてしまう場合がありますので注意してください。
お問合せ・ご相談はこちら
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
| 対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
|---|
無料相談実施中
サイドメニュー
お役立ち情報
相続手続サポート
その他のサービス
事務所紹介
お客様相談室
フォンタナ
国際行政書士法務事務所
住所
〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12
アクセス
電車では「雑色駅」より徒歩7分
営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
主な対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など