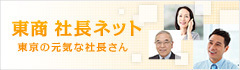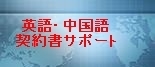大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
|---|
アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
|---|
長男が家業を受け継いで親の財産を守ってきたとか、
長女が親の監護を長い間してきたとか、
姪が子供のいない叔母の世話をしてきたとか、
本当に苦労した人は、その人なりの言い分があります。
ですので、親族間の遺産分割の協議で、
自分自身、或いは自分の配偶者等の努力、苦労に対し、
他の相続人と均等に分割されることに納得できないと
主張するケースが非常に多くなってきています。
寄与分制度とは、被相続人の財産の増加や維持、
その他、特別に寄与した人に対し、その対価として
別枠で特別に多く遺産を譲る制度です。
現実問題として、この寄与度を金銭に算出することは、
非常に困難な場合もあります。
例えば長い間、介護をしてきたのであれば、
その期間、費やした時間、内容、費用などを記録しておくのも
一つの方法です。
それらを有料の介護士や看護士に依頼した場合に換算して、
寄与分の金額を算出することもできます。
また、家業を継いだのであれば、投資をして商売を拡大したとか、
会社の株価を上げたといったことでも評価される場合があります。
寄与分の金額は、相続人同士が相談して決めますが、
親族間で合意に至らない場合は、家庭裁判所に裁定して
もらうこともできます。
しかし、裁判にまで至れば、親族の関係にも影響を
及ぼしかねませんので、晩年に特定の子供や親族等お世話になって、
そのお世話になった人に少しでも多めに相続させたい場合は、
遺言書を作成して、その理由を付言として書かれてはいかがでしょうか。
一番重要なことは、相続人全員が納得できるように、
ご自身の意志を明確に遺すことであると考えます。
そのことが、自分の面倒を看てくれた人への感謝の
気持ちを伝えることではないでしょうか。
現時点では、寄与分の認定は非常に困難のようですが、
永年に渡り妻が舅の介護をしていた場合などは、
積極的に寄与分を認めるべきではないかといった議論がなされ、
相続法の大幅な改正が審議されています。
特別の寄与の制度が新設されました。
寄与分を認める遺産分割協議書の書き方
原則的に寄与分は共同相続人全員の協議によって決められ、
本来の相続分の修正と考えられます。
つまり、寄与分は相続分と一体であり、
独立した権利ではありません。
遺産分割協議書を作成する場合、
法的には、「法定相続分として〇〇、寄与分として〇〇を相続する」
といった区分を明記する必要ありません。
ただし、相続人が協議して合意した寄与分に関して、
合意に至った行為や原因を協議書に記載しておくことは、
相続人の子孫等への説明として有意義だと思います。
時間の経過と伴に、遺産分割の割合だけが事実として残り、
そこに至った理由を知らされていない子孫が疑念を抱かないような
配慮が必要ではないでしょうか。
例えば、父親の相続の時に、相続人全員が長男に寄与分を認め、
長男が多くの遺産を相続し、二男の相続分が少なかったような
場合において、後年、母親の相続が発生した際に、
二男は既に死亡していたため、その子が代襲相続人となり、
前の相続の寄与分を認めた原因を知らなかったために、
父親(祖父)の相続が不公平であった主張するようなことも
十分に考えられます。
特別寄与料の新設
令和元年7月1日以降に発生した相続に関して、特別寄与料が新設されました。
相続人でない人が被相続人を介護したような場合に、
その貢献に応じた金銭の支払いを請求できる制度です。
「特別の寄与に関する処分調停申立書」にて家庭裁判所に請求します。
申立てをできるのは、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族です。
また、「無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと」で、
「特別な寄与」が必要とされています。
つまり、通常期待される程度の貢献は含まれません。
寄与料の金額は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額等を考慮し、
介護報酬日当、療養看護日数、裁量割合を掛け合わせて算出されます。
また申立てできる期間は、相続開始および相続人を知った時から
6か月以内、および相続開始時から1年以内で、
遺産分割調停に先立って申立てをすることもできます。
勘違いされる方が多いようですが、親族ではない友人や近隣の方が行った
介護、看護等は、たとえ寄与したとしても特別寄与料は請求できません。
お問合せ・ご相談はこちら
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
| 対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
|---|
無料相談実施中
サイドメニュー
お役立ち情報
相続手続サポート
その他のサービス
事務所紹介
お客様相談室
フォンタナ
国際行政書士法務事務所
住所
〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12
アクセス
電車では「雑色駅」より徒歩7分
営業時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
主な対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など